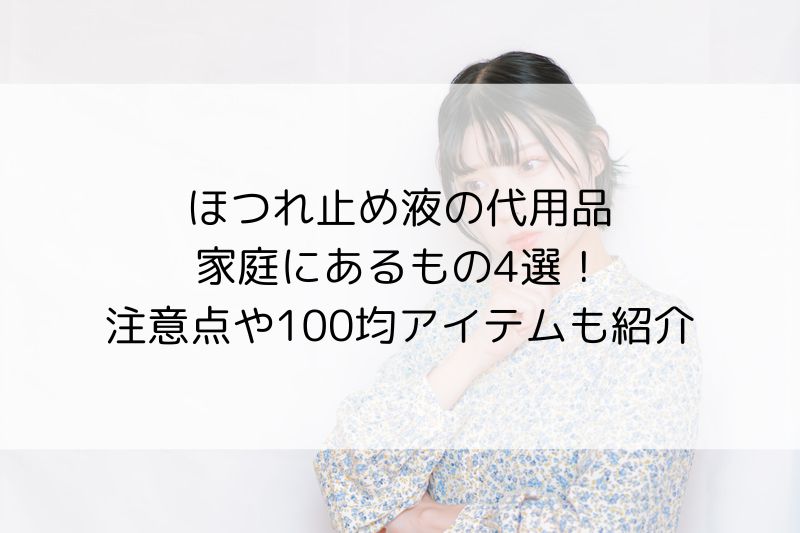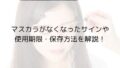裁縫や手芸をするとき、ほつれ止めは欠かせない作業です。
市販のほつれ止め液は便利ですが、すぐに使い切ってしまいコストがかかることもあります。
そこで、家庭にあるものや100均で手に入るもので代用できないかと考えることもあるでしょう。
幸いなことに、家庭にある身近なアイテムや100均で手に入る材料でもほつれ止めの役割を果たせるものがいくつかあります。
しかし、これらの代用品は素材や作業手順、洗濯方法によって適不適があります。
この記事では、それぞれの代用品の使い方や、作り方、注意点、選ぶ際のポイントについて詳しく解説します。ご参考になれば幸いです。
ほつれ止め液の代用品

以下で、ほつれ止め液の代用品を4つご紹介します。
たいていのアイテムはご家庭にあるので使えるものもあるでしょう。
1. マニキュア
ほつれ止めとして使う場合は、透明なトップコートを選ぶと良いでしょう。色付きのマニキュアだと、生地に色が透けて見えることがあります。
マニキュアをほつれ止めとして使う際には、次の点に注意してください。
・においが強い
マニキュア特有の強いにおいが気になる場合は、換気の良い場所で作業するか、他の代用品を試してみると良いでしょう。
・塗りにくい
マニキュアはドロッとしていて広範囲に塗るのが難しいため、小さなポイントごとに少量ずつ付けていくと良いです。速乾タイプを使うと、乾燥時間を短縮できます。
マニキュアの特性を理解し、適切に使うことで、手軽にほつれ止めをすることができます。
2. 木工用ボンド
100均で購入できる上、家庭に常備されていることも多いので、すぐに手に取れる便利さがあります。
しかし、木工用ボンドを使用する際には、以下のデメリットを考慮する必要があります。
・水性で水に弱い
洗濯機での洗濯には耐えられないため、手洗い程度のケアが必要です。
・硬く固まる
完全に乾くと硬くなり、縫うことができなくなります。
・乾燥に時間がかかる
乾燥するまでの時間が長く、次の工程に進むまで待たなければなりません。
・ドロッとしている
そのままでは使いづらいため、水で薄める手間がかかります。
・乾燥後に目立つ場合がある
透明になるものの、固まりとして目立つことがあります。
木工用ボンドを使う際は、水を少しずつ加えてサラサラになるように調整しながら使用すると、扱いやすくなります。また、水に浸けると白濁しますが、乾かすと再び透明に戻ります。
3.布用ボンド
これらは水で薄める必要がなく、そのまま使えるのが特徴です。木工用ボンドと同様に水溶性で透明になるため、目立つ場所には使いにくいという欠点があります。
特に『裁ほう上手』といった布用ボンドは、ほつれ止めにも非常に使いやすいです。
このボンドはアイロン掛けが必要ですが、しっかりとほつれを防ぎ、洗濯やクリーニングにも対応しています。
ただし、アイロンをかけた後は硬くなるため、使用場所によっては注意が必要です。
4. 布用両面テープ
種類が豊富で、水に強いタイプのものを選べば、洗濯も可能です。
布用両面テープの主な特徴は、強い粘着性です。
この特性により、貼った後に手縫いやミシンでの処理を行うと、針に粘着成分が付着してしまい、ベトベトになることがあります。
最悪の場合、針が折れてしまうこともあります。そのため、布用両面テープだけで処理する場合に使用するのが良いでしょう。
ほつれ止め液の代用品として、家庭にあるアイテムや100均で手に入る材料を活用する方法を紹介しました。
裁縫や手芸の際にこれらの代用品を上手に使いこなして、コストを抑えつつ便利に作業を進めてみてくださいね!
自宅で簡単にできるほつれ止め液の作り方
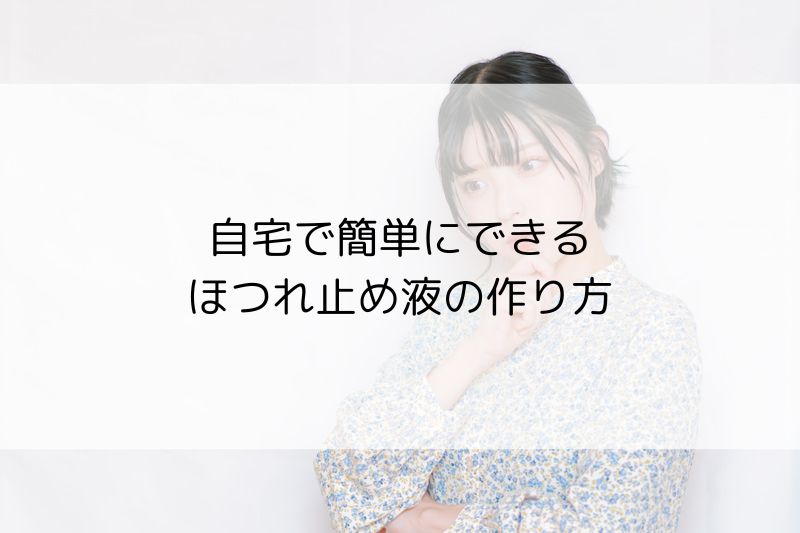
必要な材料と道具
・液体のり:市販のものが手軽で便利です。粘着力が強いものを選ぶと、より効果的です。
・水:できれば精製水を使用することで、より品質の良いほつれ止め液が作れます。
・小さな容器:密閉できる容器を選ぶと保存が簡単です。ガラス製やプラスチック製が適しています。
・かき混ぜ棒:竹串やプラスチック製のスティックが便利ですが、割り箸でも代用可能です。
・ブラシまたはスポンジ:小さい布地に使いやすいサイズのものを選ぶと便利です。ペイントブラシやメイク用スポンジも代用できます。
基本的な作り方
小さな容器に液体のりを適量入れます。この際、容器の大きさによって適切な量を調整してください。
液体のりの量が多いほど、濃度が高くなり強力なほつれ止め液が作れますが、薄い布地には適量を心がけましょう。
水を少量加えます。
水を加えたら、かき混ぜ棒を使ってゆっくりと混ぜ始めます。
液体が均一になるまで丁寧に混ぜ続けてください。
液体がムラなく混ざり合い、なめらかなテクスチャーになったら完成です。
混ぜる時間を少し長めにすることで、より安定した仕上がりが期待できます。
自作ほつれ止め液の効能と効果
自作のほつれ止め液は、生地のほつれを防ぐだけでなく、裁縫作業を簡単にする効果があります。
この液体を使用することで、ほつれた部分をしっかりと固定し、後の作業がスムーズになります。
また、この液体は特に薄手の布や繊細な素材にも適しており、扱いが難しい生地にも安心して使用できます。
さらに、必要に応じて液体の濃度を調整することで、幅広い用途に対応可能です。
これにより、裁縫の初心者から慣れている方まで、誰でも簡単に活用することができます。
ほつれ止め液の成分について
裁縫を楽しむ人にはおなじみのKAWAGUCHIのピケは、主にナイロン樹脂とアルコールで構成されています。
このナイロン樹脂は、水分で薄められているため、使用後もきれいな仕上がりが保たれます。
一方、木工用ボンドの主成分である酢酸ビニル樹脂は、水分が蒸発することで固まる性質を持っています。そのため、洗濯などで水に浸かると、水分が戻って元の状態に戻ってしまうことがあります。
だから、KAWAGUCHIのピケのイメージで木工用ボンドを代用品として使うと「あれ?」と思ってしまうでしょう。
100均で手に入るほつれ止め液
ほつれ止め液は100均でも手軽に購入できます。近くに100均があるなら、探してみると良いでしょう。
ダイソー
商品名は「ほつれ止め液」です。ピケの3倍量が入っているため、とてもお得です。使用感としては、以下の特徴があります。
・乾燥後の固さはピケよりも柔らかい
・ダイソーの方がさらさらしている
ただし、ダイソーのほつれ止め液は洗濯には向かず、一度洗濯するとほつれが出てしまうことがあります。取り扱いがない店舗もあるため、見つからない場合は店員さんに確認してみましょう。
セリア
商品名は「布地のほつれ止め液」です。ピケのナイロン樹脂とは異なり、ウレタン樹脂を使用しています。
薄手の生地には向かず、撥水加工やシルクなどでは乾燥後に白くなる可能性があります。
使用前に一度ハギレで試してから使うことをおすすめします。洗濯が可能なのがポイントです。
キャンドゥ
セリアと同様にウレタン樹脂を使用しています。薄手の生地に使う場合は、事前にハギレで試してみると安心です。
ほつれ止めを代用品で済ます時の注意点
代用品を使ってほつれを防ぐ際に注意すべきポイントは次の4つです。チェックしておいてくださいね。
・ミシンや手縫いで追加処理をするか
・乾いた後に目立たないか
・素材が薄手かどうか
これらのポイントを重視しながら、適切な代用品を選びましょう。
●洗濯や水洗いをする予定がある場合
マニキュア、水に強い布用ボンド、セリアのほつれ止め液が適しています。
●ミシンや手縫いで処理を追加する場合
マニキュアや100均のほつれ止め液が良いでしょう。
●目立つ場所の処理
透明なトップコートや100均のほつれ止め液がおすすめです。
●シルクサテンやオーガンジーなど薄手の素材
透明なトップコート、布用ボンド、100均のほつれ止め液が適しています。
●それ以外の場合
マニキュア、木工用ボンド、布用ボンドが使いやすいです。
ご家庭にあるアイテムでほつれ止め液の代用をする場合、ケースバイケースでピタリと合うものが変わってきますね。
ほつれの原因と対策
ほつれが起きる生地の特徴
ほつれが起きやすい生地には、繊維が緩く編まれたものや、切りっぱなしの布端があります。
これらの生地は、織り方や構造の特性から繊維が摩擦や引っ張りに弱く、簡単にほつれてしまう傾向があります。
例えば、シフォンやオーガンジーのような薄手の生地や、手編みのニット素材などが典型的です。
特に、切りっぱなしの布端は縫製されていないため、短期間でほつれが広がりやすい状態にあります。
また、繊維の種類や加工方法によってもほつれやすさが異なり、化学繊維と天然繊維ではその性質が異なります。
これらの要因を理解することで、適切な対策を講じることが可能です。
ほつれを防ぐためのコツ
布端を縫い代で処理することで、布のほつれをしっかりと防ぎます。
縫い代の幅を広めに取ることで、さらに強度が増し、長期間使用してもほつれにくくなります。
ジグザグミシンやオーバーロックミシンを使用することで、布端を丁寧に処理できます。
これらのミシンは、生地に合わせたステッチを選ぶことで、見た目も美しく仕上げることができます。
オーバーロックミシンは特にカットと縫製を同時に行うため、作業効率が大幅に向上します。
そして当然、ほつれ止め液を使用するのも効果的です。
この液体は、布の端に塗布することで、繊維のほどけを防ぎます。
特に薄手の生地や繊細な素材に対しては、優れた効果を発揮します。
また、乾燥後も柔軟性を保つため、布の質感を損なうことなく使用できます。用途に応じて適量を塗布するのがポイントです。
まとめ
ほつれ止め液の代用品としては、
●狭い範囲のほつれ止めには、マニキュアのトップコート
が適しています。
薄める手間やにおいが気になる場合は、手間をかけずに済む100均のほつれ止め液を使うのが簡単です。